特別支援学校に7年勤務した経験を持つ筆者が、生活単元学習の授業のアイデアを紹介します。
生活単元学習の授業を任せられたけど、どんな授業をすればいいの!?とお悩みのあなたに。
来年度の授業計画に役立つ情報満載!
生活単元学習って何!?
児童生徒が生活上の目標を達成したり、課題を解決したりするために、一連の活動を組織的に経験することによって、自立的な生活に必要な事柄を実際的・総合的に学習する指導の形態。この指導では、広範囲に各教科等の内容が扱われる。また、児童生徒の学習活動が、生活的な目標や課題に沿って組織される。指導にあたっては、必要な知識や技能の獲得とともに、生活上の望ましい習慣・態度の形成を図り、身に付けた内容が生活に生かされるようにすることなど、考慮されている。
文部科学省 資料3 知的障害のある児童生徒のための各教科について
かいつまんで説明すると、
生活単元学習とは、国語・算数のような教科だけだと、学習した能力が身に付きにくかったり、自分の生活に応用するのが苦手だったりする知的障害がある子どものために作られた授業です。
各教科を合わせた指導といって、国語・算数、音楽、図工、体育など様々な教科の要素を組み合わせてより実生活に近い授業を作ることができますよ。

小学校だと生活科や総合の授業に近いかな。
授業アイデア
では実際に実際に行ったり、他学年で行っていていいなと思った授業をご紹介!
カメラマンになろう!

年間を通して行うのにおすすめの単元!
生活単元学習では校外歩行を取り入れることが多いのですが、ただ歩くだけだと授業としてはちょっと弱い・・・
そんなときには、「カメラマンになろう!」
学校の周りにある公園や公共施設などを歩行で訪れてカメラで撮影します。教師が子どもを撮影してもいいけど、なるべくなら子どもがカメラで撮影できるとなお良し!
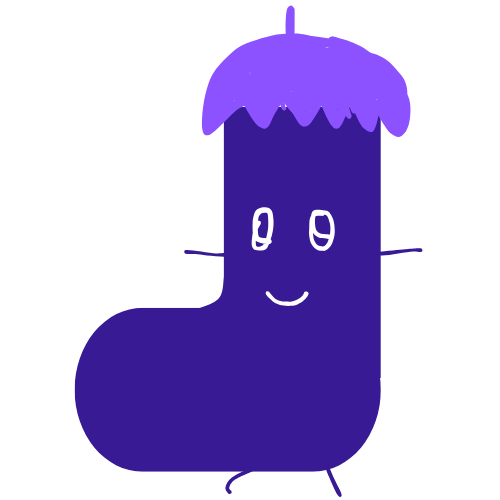
でも、子どもがカメラで撮影するとブレたり、フレームアウトしてたりするよ・・
心配ご無用!回を重ねるごとに上達するし、そんな写真も子どもの味が出る!

子どもが撮っている様子をさらに教師が撮影すると、授業の振り返りで使えるよ!
撮った写真で、みんなで学校の周辺地図を作るもよし、画用紙に貼ってアルバムを作るもよし!
電車(バス)に乗ろう!

これまた、校外歩行とからめた学習。学校によっては、遠足で公共交通機関を使う学校も。そのための事前学習としても使えます。
子どもって乗り物好きな子多いですよね。特に自閉症の子は電車が好きな子が多い!時刻表や路線図、電車の種類など、物知り博士がいっぱいです。
そんな子どもたちの心をつかんで離さない乗車学習。実際に校外に出る前に、使う駅の名前や乗車のマナー、ICカードや現金での支払い練習など、利用にあたって必要な力を授業で身につけましょう。

ご利用は計画的に!だね!
この単元の注意事項は、お金が関わるということ!交通費は学校から予算が出ると思いますが、事前の申請が必須です。学校によっては年度初めに計画を立てていないと実施できないということも!また、ICカードを利用する場合は、各家庭に協力をしてもらう必要があります。保護者会や面談等で、事前に説明をしておくことも大事!
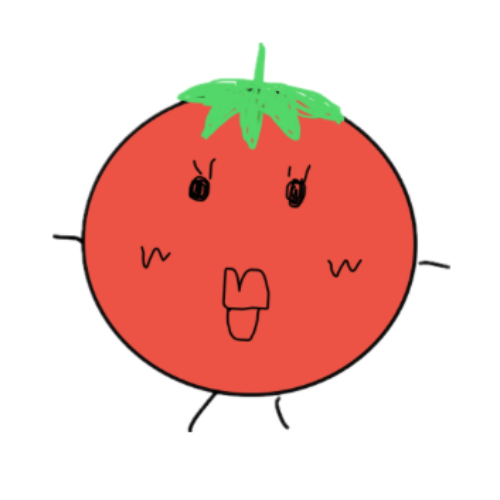
ICカードを持ってきてもらうのであれば、紛失にはくれぐれも気を付けるのよ!
公共交通機関に乗るということで、騒いだりほかの人に迷惑をかけたりしないか心配になるでしょう。実際にシミュレーションをしながら担任同士で綿密な打ち合わせを行ってくださいね。
それでも、手間をかけるだけあって、子どもたちは1週間も前からウキウキしていたり、「電車!」とまたやりたい気持ちを伝えてくれたりと良い反応を見せてくれます。しかも、回数を重ねるごとにマナーや支払いが上手になっていきます!
また、家庭だとなかなか公共交通機関に乗せられない家庭も多く、保護者からも「学校で練習してくれてありがたい!」と感謝されることも。
目指せ!お掃除名人!

2~3ヵ月で行うのがおすすめな単元!
生活するうえで必要な力、掃除。まさに生活単元学習の目標、実生活に役立つ授業ですね。
自分の教室をキレイにして居心地の良い空間をつくるもよし、学校の共用スペースをキレイにして周りの先生たちに褒めてもらうもよし!
将来、清掃の仕事に就く子どももいるかもしれません!
ということで具体的な掃除内容。
・雑巾がけ
廊下などある程度距離のある場所で!スタートとゴールがはっきりわかるコースを設定すると、子どもたちが理解しやすいよ。レース勝負のようにゲーム性を入れるのも◎。
雑巾が滑りにくい場合は、雑巾の下に床拭きシート(ドライタイプ)を入れるといいですよ。

高這いの姿勢でやるから、体育との結びつきもあるね。
・モップがけ
まだ高這いの姿勢をキープするのが難しい子にはこれ!
体育館で使うような大きなモップで廊下を掃除しよう!
一つのモップで使い終わったら次の友達に渡す、という流れにすれば友達への意識も高まります。
・上履き洗い
金曜日に実施をおすすめします。いつもなら家庭に持って帰って、保護者が洗ってるかもしれない上履きを自分たちで洗おう!
子どもの実態に合わせてブラシの大きさや形状を選びます。石鹸もスプレータイプのものだと子どもが使いやすいですよ。
洗う順番、石鹸スプレーをかける回数、こする回数、などを手順表に入れてあげると良い視覚支援に。
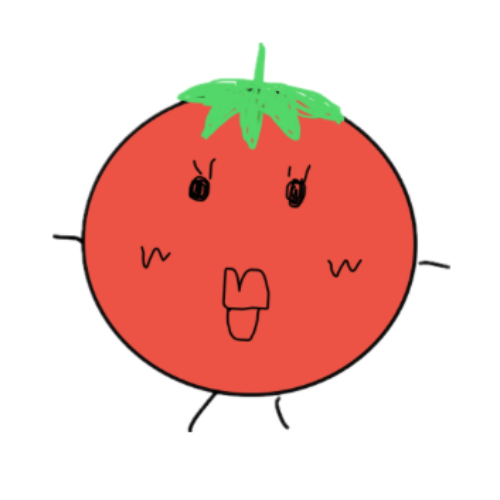
洗う場所に合わせて、どんな形状のブラシを使ったら洗いやすいか子どもに考えさせるのもいいわね。
・掃除機
まずは、ゴミを吸わせる練習から。小さい折り紙などを床にばらまいて、全部吸ったらおしまい!
迷路のようなコースを作って、一方通行でゴールにたどり着いたらおしまい、という流れも子供に分かりやすくておすすめ!
・台拭き
給食前の机拭きにも活かされる!拭き残しがないように、拭く順番を教えてください。
清掃の仕事に就く際には、会社から掃除の手順を教わると思います。その手順を今のうちから習得出来たらお得ですよね!
筆者の学校では、「公益社団法人東京ビルメンテナンス協会」のやり方にのっとっていました。リンクページの下の方に特別支援教育「清掃マニュアル」がありますよ。
台拭きを絞るのも、手先や手首を使ったよい練習に。国語算数や自立活動につながります。
・ゴミの分別
教室に赤(燃える)のゴミ箱、青(燃えない)のゴミ箱って置いてありますよね。
子どもに捨ててもらおうとゴミを渡すと、毎回「どっち?」って聞かれたり、間違ったほうに入れたり。
そんなお悩みにこれ!みんなでゴミ分別ゲームをやろう!
ゴミの種類や分別の手がかりは子どもの実態に合わせてくださいね。弁別するというのは国語算数の課題にもつながります。
お手紙をだそう!

作り物の単元です。手作りのはがきを作って、実際に郵便ポストに出しに行きます。
筆者は学校で飲む牛乳の空きパックを使ってはがきを作りました。紙漉きセットが学校にあったのでそれを使いました。型や網が入っているので便利です。
学習内容はこちら。
・はがきづくり
牛乳パックをあらかじめ茹でておき、フィルムをはがしやすくしておく。子どもたちは両側のフィルムをはがして、小さくちぎる。
ちぎった牛乳パックと水をミキサーに入れてドロドロに。液体をはがきの型に入れ、水気をきる。水気が切れたら窓に貼ると太陽光で乾き、乾いたらそのまま剥がせます。
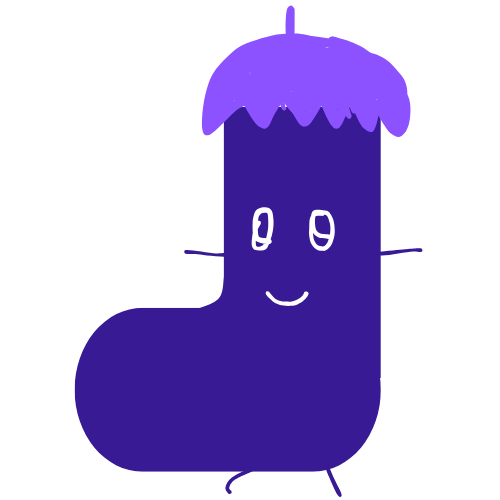
ミキサーに入れるときに花紙やラメを入れるとはがきが可愛くなるね。
・はがきにメッセージを書く
スタンプを押したり、ペンで絵をかいたり、メッセージを書いたり、好きに装飾を。家庭に送ると子どももやる気が出るし、保護者も喜びますよ。
手作りのはがきなので、ボロボロに崩れることも。筆者は郵便局に確認し、テープで補強しました。
・ポストに投函
校外歩行でポストまで歩きに行こう。事前にポストに投函する練習をするのもいいですね。
季節を感じよう!

年間を通して行うことができる単元です。日本にはせっかく「春」「夏」「秋」「冬」の4つの季節にそれぞれのイベントがあるのだから、それを体験しないのはもったいない!
5月:「こいのぼりをつくろう!」
画用紙でこいのぼりの工作をしたり、大きなビニール袋にウロコを貼って子ども自身がこいのぼりになったり、近くに飾られるこいのぼりを見に行ったり。
7月:「たなばた飾りをつくろう!」
画用紙でたなばた飾りを作って飾ったり、お願い事を書いたり、たなばたの物語を聞いたり。笹を飾れたらなおよし!
7月:水遊びをしよう!
暑くなってきた時期に!校庭でビニールプールを出してもよし、水風船や水鉄砲で遊ぶもよし、スーパーボールすくいをするのもよし!学校だからこそ、汚れるのも濡れるのも全力で楽しみましょう!
9~10月:おつきみをしよう!
白玉粉を使ってお月見団子を作ったり、白いお手玉をお月見団子に見立てて積み上げゲームをしたり、影絵で遊んだり。
10月:ハロウィンパーティをしよう!
みんなで仮装大会!校内を練り歩いてお菓子を配るのも楽しい!粘土などであらかじめお菓子作りをするのもいいですね。
12月:クリスマスパーティーをしよう!
クリスマスオーナメントづくりやクリスマスソングでカラオケなど!サンタさんに扮した先生がプレゼントを配りに来たら盛り上がるかも!
1月:雪で遊ぼう!
雪が降る地域だったら外で雪遊びをするのもいいですね。教室で雪に見立てたボールで雪合戦も!
2月:節分をしよう!
鬼のお面づくりや豆作り、実際に鬼退治も!筆者の学校では、本格仮装をした先生が全力で脅かしに来てくれていました(笑)
3月:1年間を振り返ろう!
3月は授業日数も少ないので(しかも教員としては、年度末書類でバタバタの時期)、今までの行事を写真や動画で振り返るのがおすすめ!
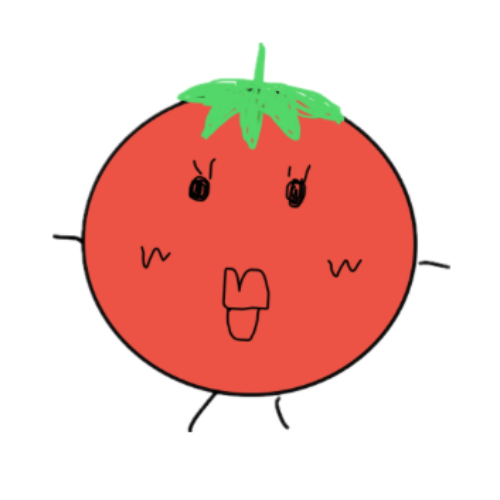
事前にたくさん写真や動画を撮っておくことね!

どの行事も家庭だとなかなかやってあげられないことが増えてきたから、学校でやると喜ばれます。
行事に絡めてグッズを作ることは、将来作業所で働くときに役に立つことも!実際に地域の作業所に見学に行ってみると、イメージがわきやすいですよ。
今は、作業所で作った商品が通販サイトに掲載されていたりするので、そちらを見てみるのもいいですね。
移動教室に行こう!

行事に絡めた事前事後学習です。移動教室といえば高学年に行う宿泊を伴う一大イベント。筆者の学校では2学年合同の行事で、事前事後学習も合同で行いました。
学習内容はこちら。
・2日間のスケジュール確認
移動教室ではどこにいくのかな?どんなことをするのかな?ごはんは何を食べるのかな?確認することはたくさんあります。画像や動画を入れてパワーポイントで紹介するのがおすすめです。
・お風呂の入り方、布団の敷き方
普段の学校生活ではやらないお風呂や就寝。共同生活では、自分のことは自分でやらなくてはなりません。体の洗い方や拭き方、布団の敷き方を実際に練習してみましょう。音楽に合わせてダンスのように体の洗い方を練習したり、布団の代用としてタオルケットを敷いてみたり、実際に体を動かしてやってみよう。
・レクリエーション練習
宿泊施設についたら、運動ゲームやダンスなどのレクリエーションを行います。せっかく2学年合同なのだから親睦も深めましょう。当日に行うレクリエーションを練習します。
・買い物練習
せっかくの移動教室、何か記念になるものを買いたいですよね。お菓子やキーホルダーなど好きなものを選ぶ練習、レジで支払う練習など、買い物練習も行いましょう。
・事後学習
行事が終わったら、振り返りも行いましょう。写真や動画で振り返ったり、自分の写真を画用紙に貼って、自分だけの思い出アルバムを作るのもおすすめ!
遠足に行こう!

こちらも、行事に絡めた事前事後学習。遠足と言ったら、「動物園」や「水族館」が定番ですかね?
動物の名前や水の生き物の名前を実際に見ながら覚えられる良い機会です。事前の学習で、どんな生き物がいるのかを確認したり、スタンプラリー形式で見学するのもおすすめです!
筆者は、「水族館」に遠足に行った際には「さかな」づくしな事前学習を行いました。
学習内容はこちら。
・さかなでパズルをしよう!
Ipadのアプリで水族館にいる生き物の写真でパズルを行いました。
・さかな釣りをしよう!
塗り絵をして、釣る魚を作るところからスタート。割りばしで作った釣り竿も紐の長さやマグネットの大きさなどを実態に応じて変え、難易度を設定しました。
・さかなを探そう!
校舎のいたるところに水族館にいる生き物の写真を貼り、校内スタンプラリーをしました。校内を並んで歩くことで実際に見学するときの練習にもなります。
ピザパーティをしよう!
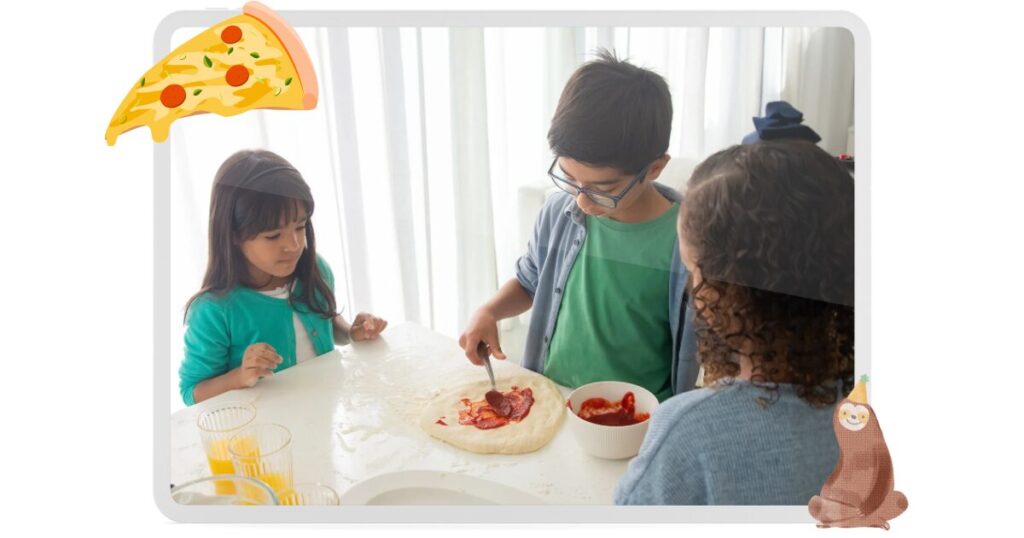
調理学習と買い物学習のコラボ授業です。
筆者の学校では餃子の皮を使ってピザを作りました。
近所のスーパーにピザの具材を買いに行き、それを使って調理をします。

アレルギーがある子どもがいるときは具材に注意してね!
・買い物編
近所のスーパーまで歩きます。スーパーの中は誘惑でいっぱい!数人ずつ買い物に出るのがおすすめ!
買い物をするスーパーにはあらかじめ電話などで事情を説明しておくと連携が取れて学習がスムーズですよ!
「品物を探す係」「かごやカートを持つ係」「お会計係」など役割分担をしよう。
品物を探したり、会計が難しい子も、スーパーの中をみんなと歩いたり、買った品物を学校まで持って帰ったりすること自体が立派な学習になりますよ!
・調理編
調理の前には身支度が重要!手洗いやエプロン、三角巾、マスクをつけることを忘れずに!
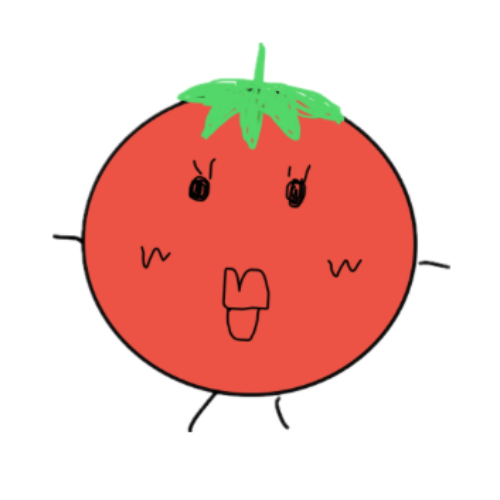
いずれ飲食系の仕事に就くかもしれないし、しっかり練習しておいて損はないわ。
クッキングシートに名前を書いておき、自分で作ったピザが自分で食べられるようにしてあげよう。
買った具材を小分けの皿に入れて子どもに配り、自分の好きな具材がトッピングできるようにしよう。
自分で作ると、普段は偏食であまり食べたがらない子どもが食べてくれたりするよ。
まとめ
生活単元学習は、子どもたちが実際に生活につながる力を育てる大切な時間です。まずは、できる活動から一つだけ取り入れてみてください。
手順表や役割分担を工夫するだけでも、子どもたちの取り組む姿が大きく変わります。明日からの授業づくりの参考になれば嬉しいです。





コメント