特別支援教育で重要な実態把握。
いったい何をどうやって把握すればいいのか・・・?
特別支援学校勤務経験のある筆者が解説します!
実態把握をする理由
ズバリ!担任になったら必ず作成する、個別の指導計画を作るため!
指導計画とは、子どもが今持っている力を使って、その少し上の目標を達成できるようにどんな指導をするのか記入する書類です。学期末には、指導の結果子どもがどのように成長したのかを記入し、保護者に成績表として配布します。
実態把握のやりかた

やることはたった1つ。とにかく観察すること!
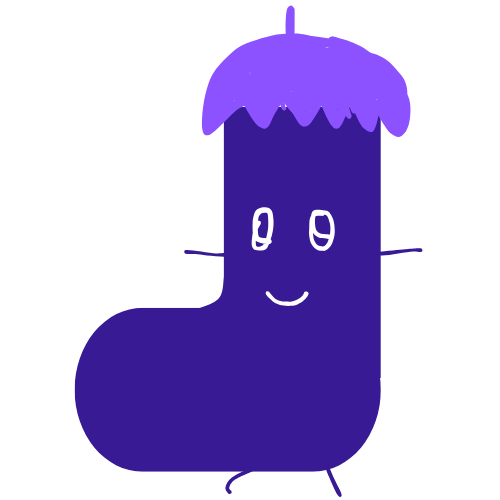
それだけ?もっと難しいのかと思った・・・
観察といってもただ子どもを見つめればいいというわけではありません。
具体的に何を見ればいいのか、場面ごとにポイントを確認していきましょう。

ただ「できる」ではなく、
「教師が見ていなくてもできる」
「教師が見守るとできる」
「教師が言葉をかけて促すとできる」
「教師が身体介助を行うことでできる」
というように具体的に分析しよう!
身支度面
荷物整理
・リュックから自分の荷物を出すことができるのか。
・自分の名前やマーク、色で荷物の置き場所を理解できるか。
・机と荷物置き場の距離は近い方がいいのか、遠くても大丈夫なのか。
・「タオル」「連絡帳」などの音声と実物は一致して理解できているのか。
着替え
・シャツやズボンを介助者に脱がしてもらう場合、協力動作がでるか。
・シャツやズボンは自分で脱げるか。
・ズボンは立位で脱げるのか。
・裏返しにならないように脱げるか。
・シャツやズボンを履くことができるか。
・裏返った袖を直すことができるか。
・服をたたむことができるか。
・上履きの脱ぎ履きができるか。
・肌着をズボンの中に入れられるか。
・服の前後を間違えずに着られるか。
トイレ
・オムツなのか布パンツなのか。
・尿意はあるか。定時誘導で排泄するのか。
・男子なら立ち便器を使えるか。
・トイレットペーパーを自分でちぎることができるか、自分でふき取ることができるか。
・トイレに行くことを他者に伝えられるか。
・月経をがあるか。
・大便を学校ですることがあるか。
・手を洗うことができるか。(両手をこする、石鹸をつかう)
学習面
〈集団学習〉
・集団授業への参加態度はどうか。(前方への注目、離席、ノリのよさ、友達へのちょっかい)
・音声指示への理解度はどのくらいか。
・MTへの促しや問いかけへの反応はどうか。
・全体でのあいさつに応じることができるか。
・模倣はできるか。
〈個別学習〉
・目の前の教師のあいさつに応じることができるか。
・学習への集中時間はどのくらいか。
・机上学習への意欲はどうか。(たまに机に座ることを拒否する子どもも)
・利き手はどっちか。
・発達検査の結果。
・色や身近なものの名前、文字、数字への関心や理解度はどうか。
・手先の器用さはどうか。
・目の動きはどうか。(左右、上下、追視)
・書字の能力はどうか。
食事面
・食形態はどうか。(初期・中期・後期・普通)
・食具は何を使っているか。(スプーン、箸、補助食具)
・好き嫌いはあるか。
・偏食はあるか。
・食べる速度はどうか。
・ストローを使えるか。(牛乳パックをストローで飲む場合)
・牛乳瓶を開けられるか。
・食器の片づけはできるか。
・食べこぼしはどうか。
コミュニケーション面
・発語はあるか。
・コミュニケーション手段。(言語・音声・絵カード・サイン)
・指さしはあるか。
・教員からのアクションへの反応。
・友達とのかかわりかた。(友達同士の相性も)
行動面
・こだわりはあるか。(場所、順番など)
・パニックや他害はあるか。(わかれば原因やその前後の様子も)
・好きなこと、落ち着ける環境。
・教室外への飛び出しはあるか。
・階段昇降はできるか。(てすりの使用有無)
・まひなどによる身体補助の必要性はあるか。
・行動の切り替えはできるか。(休み時間と学習時間)
健康面
・発作やアレルギーはあるか。
・運動制限はあるか。(ダウン症のマット運動など)
・アトピーはあるか。(かゆさで学習に集中できないことが)
・花粉症はあるか。(屋外での活動への配慮)
・服薬による副反応はあるか。(ねむけ、だるさ)
実態把握が終わったら、原因を探ってみよう

子どもを観察することで、できることできないことを把握することができたと思います。
次は、どうしてできないのか、原因を考えます。ここからが教員の腕の見せ所!
身体的にできない
障害特性によっては、物理的にできない動作があります。その場合は、ヘルプを求める練習をしたり、代わりの動作を学習したり、臨機応変な指導が必要です。
周りが気になってできない
能力はあるのに、集中できない・・・特別支援学校にたくさんいます。
音が気になるのか、人が気になるのか、場所が気になるのか。
原因を分析してまずは集中できる環境を用意してあげましょう。
ゆくゆくは、あえて刺激のある環境を用意し、刺激に左右されずに安定して取り組める力を育てられると素敵です。(これには、とても専門的な観察眼と指導力がひつようです!!)
認知的にまだできない
ひらがなが読めない子にいきなり漢字を書かせたり、数字がわからない子に掛け算を教えることはないですよね?
目標の姿に達成するために必要な力を細かく分析して、スモールステップで達成するように指導することが重要です!
まとめ
いかがでしたか?
子どもの行動、視線、前後の周りの環境
子どもの行動には、その子なりの理由があるのです。推測でもその理由を考えることが子どもに寄り添う指導になるとおもいます。
素敵な学校ライフを応援しています!






コメント