もうすぐ4月、特別支援学校に入学が決まったご家庭は学用品の準備をしていることでしょう。
今回は、特別支援学校で勤務経験のある筆者が、入学にあたって必要なグッズや選び方をお伝えします。
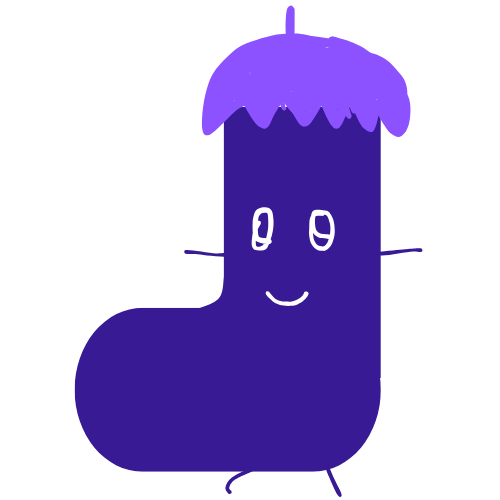
ようこそ特別支援学校へ!

このページで紹介する内容は、筆者が勤務した学校がベースとなっています。実際に入学する学校から指定された場合は、そちらを優先してね。
必ずやってほしいこと
持ち物を伝える前にすべての持ち物に共通する大切な心構えをお伝えします。
学校に持っていくすべての持ち物に記名を!
これは本当にお願いします。学校に持っていく全てのものにです。すごく手間だと思うのですが、マジックで直接書いてもよいので!
特に4月は健康診断のために服だけでなく、靴下や肌着まで脱ぐことも。トイレを失敗することもあるので、下着まで名前を書くようにお願いします。
リュックや着替えを入れる巾着も記名を忘れないようにしてくださいね。
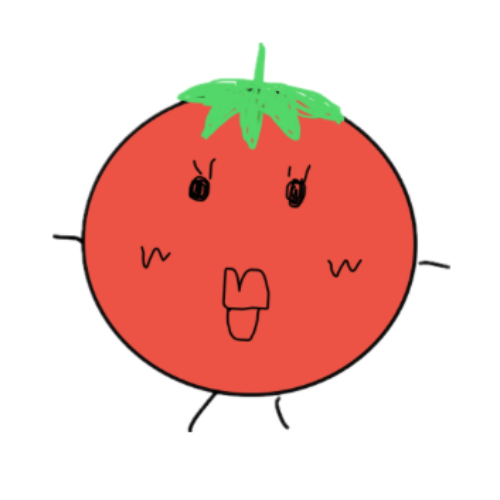
名前シールは剥がれることがあるから注意!名前が薄れてきたら、書き直すのも忘れないで。
持ち物は子どもが操作しやすいものを!
着替えを入れる巾着や連絡帳を入れる袋、毎日背負うリュックまで、最初は保護者の方が準備することが多いでしょう。でも、学校は「自分でやる」ことを目標に指導します。
例えば、体育着袋なら、きっちり畳まないと入れにくい小さめな巾着より、多少ぐしゃっと詰め込んでも服が入る大きい巾着を選んでほしいのです。
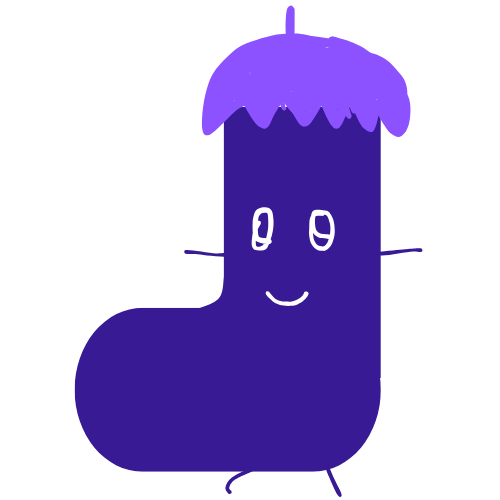
畳んでくれれば、荷物がコンパクトになるのに・・・
確かに、おうちに持って帰ってきて、リュックの中にぐしゃっと荷物が入っていて「なんでキレイに入れないの・・・?」とため息をつきたくなるかもしれません。
ただ、子どもはスモールステップで支度を練習します。しかも、手順の最後から。
どういうことかといいますと、「着替えを片付ける」手順なら
①裏返った服を直す。
②服を机の上に広げる。
③服を畳む。
④巾着に入れる。
と、4つの手順があります。ですが、いきなり4工程すべてを指導する訳ではありません。1つずつ手順を練習していくのです。(これがスモールステップです。)
そして、4工程をどの順番で指導するかというと、④→③→②→①の順番で指導するのです。なぜかというと、①から③までの手順を先生が手伝ったとしても、④を子どもが自分でやれば、達成感を感じられるからです!!
完成の瞬間に携われれば、達成感を感じられやすいのです。そこに「できたね!」と褒められたら、またやろうかな?とやる気も高まること間違いなし!
ということで、すべての持ち物は子どもが操作をしやすいものを用意していただけると助かります。

どういうものが操作しやすいのかは、担任と相談するのがおすすめ!
学校で使う持ち物!
それでは、いよいよ学校で使う持ち物を紹介します。
リュック
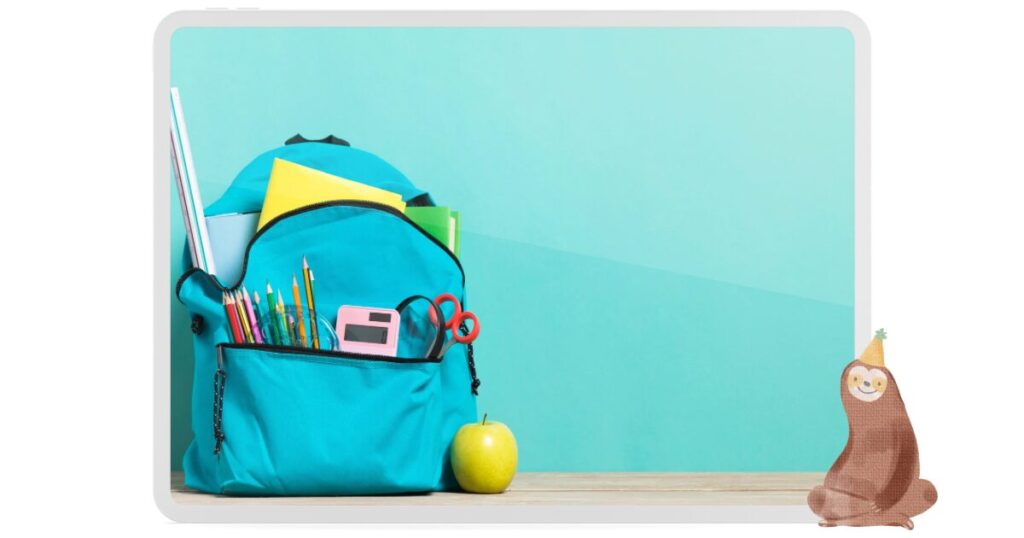
ランドセル等の指定はありません。着替えやエプロンなど布物のかさばる荷物があるので大きめのリュックをお勧めします。見た目も大事だけど機能性重視で!
背負いやすいもの、収納場所が多いもの、子どもの好きな色、などなど。
筆者の学校では、アウトドアブランドのリュックが多かったです。
ということは、同じリュックを使う子どもが複数に似る可能性があるということ。しつこいようですが、記名はしっかりお願いします。
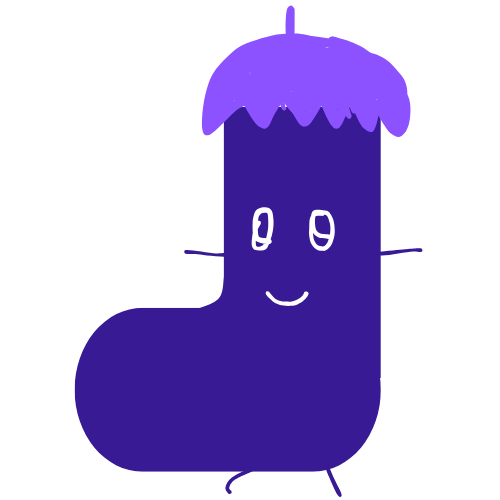
目立つキーホルダーを付けるのもありだね!
ジッパーの操作が苦手な子には、チャックに紐をつけると開閉しやすいです。
また、放課後デイサービスを利用する日は、別途サブバッグを持たせたり、リュックを変えたりすると子どもが下校後の予定を把握しやすいです。
家庭によってはお祝いでランドセルを買ってもらったのでそれを使いたい!うちの子がランドセルを背負う姿を見たい!という考えもあるでしょう。使いたければランドセルを使えばよいのです!!
確かに荷物の出し入れの観点からリュックをお勧めはしましたが、たくさんの思いが詰まったランドセルがあるのなら、それを使ってあげてください。ランドセルの左右の金具に上履きや着替え袋をぶら下げたり、荷物の多い日は手提げ袋を活用したり、やり方はいくらでもあります。
子どもも大人も納得のいく持ち物を使ってくださいね。
着替え
いわゆる体育着。毎日使います。学校生活と家庭生活を切り替える意味でも、白シャツに黒、または紺のズボンをお勧めします。素材は何でもよいです。子どもが着やすい素材で。
ユニクロでもGUでもワンポイントが付いていてもよいです。
とにかく汚れます。学校に予備も置いてほしいので、数は多めに用意してください。
入れる袋は巾着袋がいいです。子どもが操作しやすい大きさ、素材を担任の先生と相談してください。
巾着袋の柄は一度決めたらコロコロ変えないようにしてください。日によって袋が違うと、いちいち中身を確認してからでないと所定の位置にしまいにいけないため、子どもに負担がかかります。
巾着袋に用途の名前は書いても書かなくてもよいです。それよりも、巾着袋の柄が異なる方がありがたいです。(給食袋と着替え袋は同じ異なる柄の巾着袋にしてください。)そして、袋にも記名を。
また、ハンカチは登校着と体育着のどちらにも入れていただけると助かります!
給食袋

エプロンとおしぼり、子どもによっては食具(スプーン・箸など)を持参しています。エプロンはスモックタイプや多いです。子どもの実態に応じて、首の後ろをマジックテープで止める形、背中でリボン結びをする形など、レベルアップしていくのもよいでしょう。
箸はエジソン箸を持参する子が多いです。ただ、作業療法士の先生がいうには、まずはスプーンを握る練習やえんぴつ持ちで持つ練習、手首を返す練習など段階を経てから箸に移行するのが良いといわれます。エジソン箸が悪いとは言いません。ただ、エジソン箸を使ったらかといって、普通の箸が使えるようになるかというと、そううまくは進まないようです。
箸を使用する目的が何なのか。食事における子どもの最終目標は何なのかを見据えながら、食具を考えていけるとよいでしょう。

作業所などでは、仕事への補助はあれど、着替えや食事への補助はサポート対象とならないことが多いです。一人で食事が完結できることを目標として、練習を重ねられられるとよいですね。
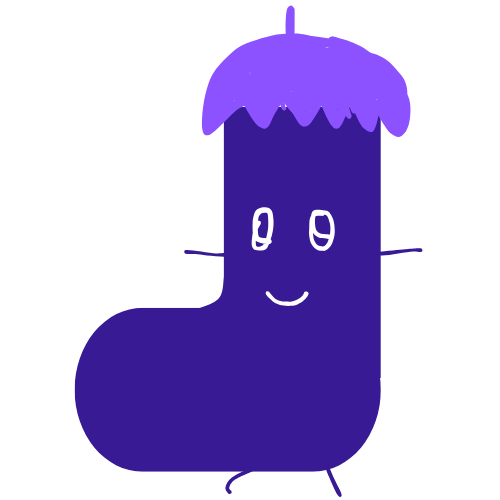
スプーンできれいに食事ができるならそれでもいいよね!
また、汚れた口や手を拭くおしぼりは、両手を使って絞るよい練習となります。ある程度雑巾のように絞りやすい大きさのものだと助かります。
上履き

これまた、さまざまな種類を使っています。よくあるバレエシューズタイプから足首まで固定するバスケットシューズタイプまでさまざまです。子どもによって足の形や筋肉の付き具合などが異なるので、子どもにあった履きやすい靴を探してください。
特に重度重複学級にいる子どもは歩行不安定な場合がおおく、かかりつけの整形外科の先生におすすめの靴を紹介してもらったり、インソールを子どもにあったものに変更したりしています。
たいていの子は、スニーカータイプやマジックテープの上履きを履いています。色は白がほとんどです。たまに登校靴と同じ銘柄の靴を用意してくれる家庭があるのですが、その場合は色がはっきり異なると助かります。
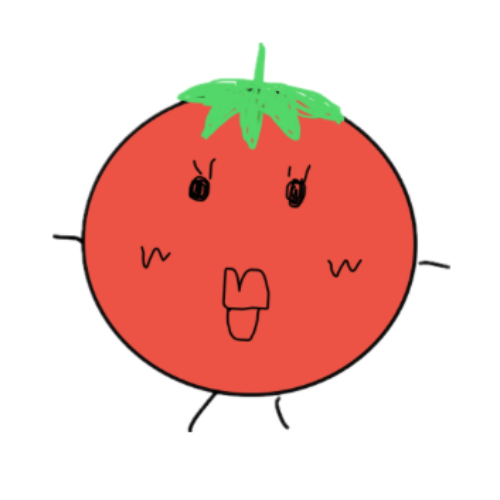
筆者は、白が上履きでクリーム色が外靴という子どもに出合い、混乱の極みだったらしいわ。
また、靴を履いてもすぐに脱いでしまう子にはコンバースの紐靴を紐をきつく結んで履かせているのも見かけました。この辺は担任との相談になるかと思います。
かかとをしっかり入れられない子は、靴のかかとにリングを付けて、それを引っ張って履くように促すとかかとを入れやすくなります。
連絡袋
毎日の出来事や体調などをやり取りする連絡帳。を入れる袋。学校によって連絡帳の形は様々でしょうが、それが余裕で入る大きさにするとよいでしょう。
ジッパーに紐をつけると操作がしやすくなっておすすめ!
図工用スモック
絵具を使った活動の際に特に活躍する図工用スモック。これも形の指定はありません。スモックタイプを着ている子が多いですが、体育着の汚れを防げればよいので、着古した大人用のシャツを持ってきてもよいです。
ただ、スモックタイプを使うのであればなるべく給食用エプロンとの併用は避け、図工なら図工だけ、給食なら給食だけに使うようにしてください。
小さい頃に絵の具のぬたくりといった感触遊びは、とても良い経験になります。(手への刺激が入りますし、感触への過敏さを慣らすがことができます)存分に活動してもらうためにも、ぜひ
「スモックも体育着もどんどん汚して!」
の精神でどんと構えてもらえると助かります。
まとめ
今回は、特別支援学校で使う学用品について紹介しました。
家庭でお試しをすることが難しい場合があると思いますが、どんどん担任の先生に相談し、子どもの自立の一歩を支えられるようにしましょう!






コメント